住民税と消費税、会社設立後に見落としがちな話
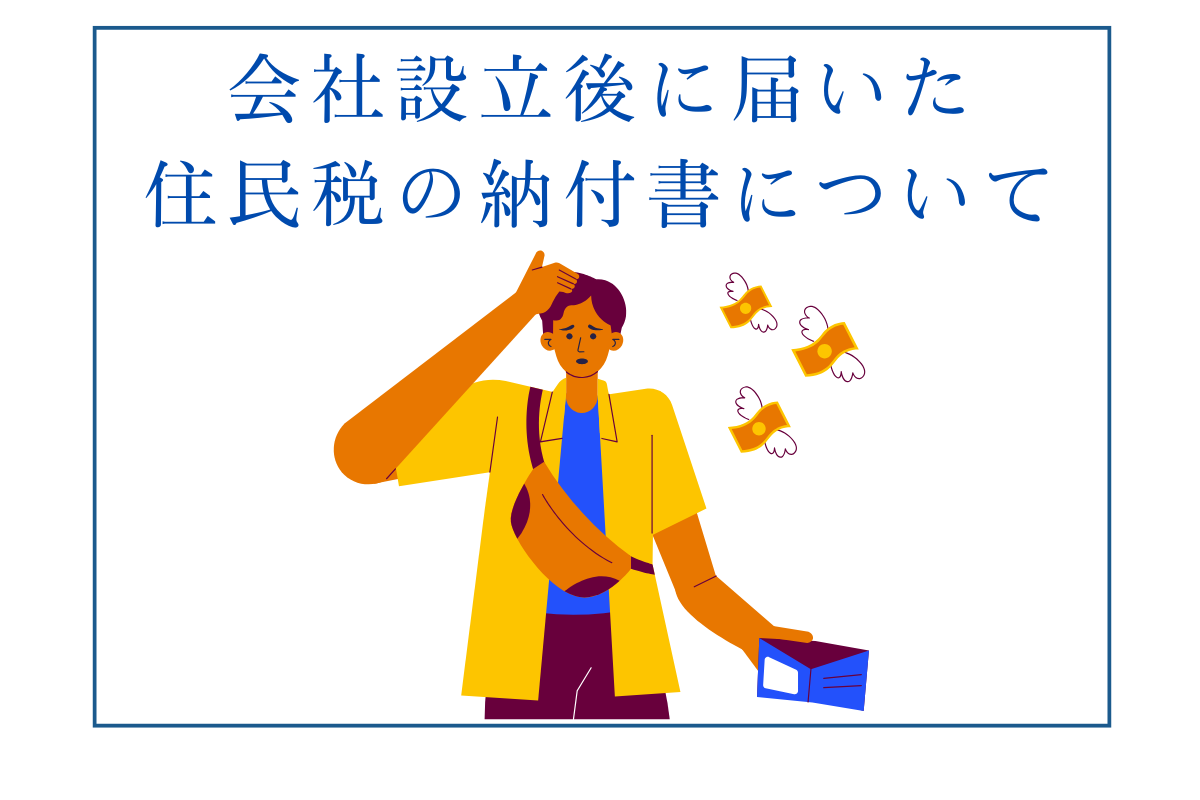
〜初年度に押さえておきたいタイミングと資金繰り〜
木戸翔太のごあいさつ
こんにちは。大阪・心斎橋で収益不動産・事業用不動産の売買仲介を専門に行っている、株式会社ビーメイン 代表の木戸翔太です。
今回は、僕自身が起業初年度に直面した「住民税の請求」と、設立後に意識しておくべき「消費税免除の条件」についてまとめました。
6月、突然届いた100万円超の住民税
住民税は遅れてやってきます。
これは税制度の基本的な仕組みの一つですが、起業や退職のタイミングでは特に意識しておくべきポイントです。
忘れていると、キャッシュフローに想像以上のインパクトが出ます。
僕の場合、2024年12月に前職を退職し、翌年5月までの住民税は、退職後に一括で支払っていました。
それで完了したと思っていたのですが、2025年6月に新たな100万円を優に超える住民税の納付書が届きました。
これは2024年の所得に対する住民税で、2025年6月から翌年5月までかけて支払う分。
制度としては理解していたつもりでしたが、創業準備の忙しさの中で完全に抜けていました。
タイミングも金額も、それなりに衝撃的でした。
起業初年度、家計へのリアルなインパクト
創業初年度は、事業を形にすることに集中する時期。
僕自身、役員報酬は最低限に設定し、家計は実質的に毎月赤字ベースでやりくりしている状況です。
そんな中での100万円を超える出費。
期ごとの支払いも検討しましたが、精神的なストレスを長引かせたくなくて、一括で支払うことにしました。
法人と家計は本来別物ですが、現実としてどちらかが崩れれば、もう一方に波及します。
会社が立ち行かなくなれば報酬は止まり、家計の貯蓄が尽きれば生活も不安定になる。
そのバランスを冷静に見ておく必要があります。
消費税の免税制度と2期目の分岐点
法人を設立すると、2期目までは原則として消費税の納税が免除されますが、条件によっては課税事業者に切り替わります。
設立から6ヶ月以内(特定期間)に、以下のいずれかに該当すると、2期目から消費税の納税義務が発生します。
- 課税売上高が1,000万円を超える
- 支払った給与・賞与の合計が1,000万円を超える
立ち上がりが順調だった場合や、人件費を厚く設定している場合などは、免税扱いのつもりでいても課税事業者になる可能性がありますので、注意が必要です。
インボイス制度との兼ね合いも重要
注意したいのがインボイス制度との関係です。
免税事業者として2期目まで運営するということは、インボイス登録を行わないという選択になります。
この状態では、取引先が仕入税額控除を適用できない可能性があるため、
相手方によっては取引に不利な条件がついたり、インボイス登録を求められることもあり得ます。
また、現時点では仕入控除に関する経過措置が存在し、登録事業者でなくても一定割合の控除が認められていますが、この割合は年を追うごとに段階的に縮小していきます。
「免税=得」という単純な話ではなく、業種・取引関係・タイミングなどのバランスを見た上で、判断する必要があると感じます。
報酬設計は短期の節税だけで決めない
役員報酬を抑えて、賞与でまとめて受け取ることで、社会保険料を抑えるテクニックもあります。
一方でこれは、将来的な退職金の算定基礎にも関わるため、短期的な負担減だけで判断すると、のちのち不利になる可能性もあります。
法人経営者にとって、報酬や賞与の設計は、自分の資産状況や家計の耐性、そして会社のキャッシュフローを総合的に見たうえで判断するべき重要なテーマです。
知っているつもりが、あとで効く
制度としては当たり前のことでも、起業の初動はとにかく多忙で、見落としが出てきやすいです。
税務の専門家ではないからこそ、最低限の知識とポイントだけは外さないように意識しておくことが大切。
そのうえで、信頼できる税理士やパートナーと連携して、細かい戦略を設計することで、ブレずに進められると感じました。
最後に
今回の記事は、僕自身のリアルな経験から得た気づきを整理したものであり、
同じようにこれから起業や独立を目指す方々にとって、何かヒントになれば嬉しく思います。
これからも、現場で感じたことや、不動産実務のリアルを発信していきますので、
ご興味のある方はぜひまた覗きに来てください。
ここまでお読みいただき、ありがとうございました。


